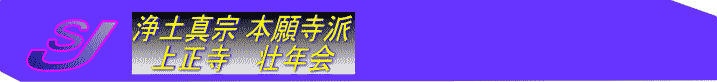
| このページに立ち入るための装備について | |
| 肩書き | 全て脱いで下さい。 (どこまで、脱げるでしょうか) |
| プライド | 全て捨てて下さい。 (どうせ捨て切れませんが) |
| 頭 | 子供のように柔らかく。(頑固・頑迷・執着は、厳禁!) |
| 知識 | ご自由に。 (全く、役に立ちません。) |
| 財産 | 持ち込む必要はありません。 無料 |
| 眼 ・ 心 | そらさずに、しっかりと開いて下さい。 |
| アルコール | 最初、若干はok。 (必ず、酔いが回ります。) |
| 同伴者 | 話し相手が必要です。 (一人では、危険が多すぎます。) |
| ☆ このページの管理は、上正寺壮年会が行っています。−問合わせはこちら ☆ これ以降に、あなたに発生するいかなる事態にも責任は負いません。 準備ができましたか? 勇気を持って前へ進む 戻る |
|
ようこそ! 正見語録のぺーじへ ここで得たものは、全て非公開です。決して口外なさらぬよう肝に銘じて下さい。 内容は、全て、上正寺壮年会が負います。 問い合わせは、こちら |
|
家族 |
{「家族」が、人間存在の基本・・・・・・・・・} ☆蓮如様の時代 「家族参り」が推奨されていました(宗雲さんフォロー) 歎異抄の「・・・一人がため・・・・」は、宗教が「個人的」と言うことではない! アメリカナイズされた、現代人(私を含め)が、「個人」を主張せざるを得ない 状況の中で、あまりに「手前味噌に」解釈している様に思うべきである。 「家族」が担う本質は、「時間」である。 子が出来、育て、孫が出来るのは、 まさに、その証左である。 言い換えれば、「社会」が、その意味を持ちうるのは、 この「時間の流れ」を保護していくこと以外には、あり得ない。 「時(とき)」は、季節の移り変わりで動くのではない。 人が「老いる」ことに よって動くのである。 若干端折って、 「子の無い夫婦」は、かなり数多くいらっしゃるが、これと、 「家族」が「時間=子や孫へ」を維持する単位であることとは、「個人」的には、 相当な意味があるとしても、あえて断言すれば、「法」の中では、「水入海一味」 でしょう。 というのは、「子や孫」は、たとえ、山奥で、1家族しかいない場合を 想定したとしても、「多くの外敵(自然を含み)」、「子が成長し、親が老いる」と いう現実のまっただ中で、必ず、「社会的」に生きるのであるから。 さらに、端折るが、「子や孫」は、どこでも、いつでも、社会的なのであって、 少なくとも、個人的な「所有感」とは別物と考えなければなりません。 「子や孫」とは、幸せにも(苦労が多いのでしょうか)お預かりした「時の流れ」 なのです。 子を持つか、持たないかの差は、「否応なく時間を意識させられるか」 それとも、「意識的に(次世代に関わる)時間に関わるか」の違いだけです。 (「子が無くとも、老いる」というように、マイナス感から出発したとしても一処です) ただ、かって「ファシズム」の理論的なバックボーンとしての「家族=国家」の ような「個人」が完璧に排除された時代があったことを忘れてはなりません。 うまく言えませんが、「個人」とは、現世にて「家族」から脱出して、「家族」を作り、 そして、老いて、「時間=恐らく<法>」に汲み取られていく存在と言えるのでは ないでしょうか? (決して、「国家」とは相容れないもののはずです。) ここまでくれば、次に、「親と子」、「夫婦」、「男と女」を問題にしなければなり ませんね。 具体的になる分、大変ですが! |
親と子 |
{時代を変える。それが「親と子」の関係本質だよ!} だけど、「子は、私の物」であり、「私の課題」であり、 もっと言えば、「私の未達の夢」であろうな!。 「教師と生徒」、「先輩と後輩」、「熟練者と新入社員」じゃないよ! 「私の所有」と言う意識は、ぬぐい去れないかもしれん。 だけど・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 現実は、この範囲から抜けることは、まず、不可能なんだろうな。 だって「親と子の年齢」は、同じと言う言い方にもある通り、 「親」の条件は、「知識量」/「経験量」/間違い量」ではない からだよ。 じゃ何よ!と言われるとして、なんと言うべきか? う〜む、なんだけど、こういう言い方は、どうかな?? <上記の量の差を埋めようとする「お互いの了解」努力の中で、 埋められないことを確認しあい(喧嘩?)、「時」が移って行く ことの「親に取っての悲しさ」と、「子に取っての優越感=不安」を、 お互いに「思いやる」関係> ちょっと、気取って言えばこんなことなのかもな!? 実は、喧嘩状態が多くって、「思いやり」が見えないこともあるだろうし、 逆に、一体化しすぎて本質が見えないまま親の死を迎える場合でも、 タイミングの差こそあれ、行き着くところは、一緒だろ!!! <巷の声> 「時代」を変える、最も身近な存在=「親にとっての子」と言う位相、 「変わって行かざるを得ない時代」を生きる術を、最も親身になって 裸を見せて(教えてではなく)くれる存在=「子にとっての親」の位相、 これが、ちょっとわかるのは、いつの時代も、「親が死んで、子が親 として、何らかの自己矛盾に陥る」時の様ですね。 ああ〜、永遠に、親と子は「矛盾」なのでしょうか?(ハムレットより) 「男と女」/「親と子」 → いよいよ「家族」ですね! こうご期待! |
男と女 |
{俺は、坊守を愛しているよ! 間違いなくな!} 「俺の第1感が、求婚した時」のことは、俺と彼女の問題。 公開するようなことではないと思う。(みんな知ってるけどね!ウフフ) 「男と女」というテーマは、恐らく「社会、または統治機構の<近代性>」 に大きく関係しており、本質的なことはいつも時代(権威)に利用されてきた。 「今は?」or「本質は?」と問われて、応えるやつは馬鹿だよ!! なぜなら、余りにも古くから問題とされてきたし、 余りにも「生」の根源的な関係性であるし、 実は、余りにも身近な問題なので、「評論」は出来るわけがない。 歴史的に、「子孫繁栄」のために大事にされたり・ 「政争」に使われたり,「女」 という「性」は、「道具」として、客体化されてきた。 (実は、「男」という「性」も本質的に同じく利用されてきた。) (すべて、「私(男も女も)」の「非了解」の上で進められてきたことだから。) ☆だけど・・・・・・ どんなに困難でも、どんなに非条理の中にあっても 「男と女」は、「一体」であり、「個」ではなく、「仲間」である。 ただし、「困難の了解」と、「非条理の理解」が共有されて、 なおかつ、<「思いやり」=「利他」>の確信が要るんだよな。 ☆これ以上、いくら議論しても、「本質」じゃないぜよ”! 「家族」カテゴリーの中で議論しなくちゃ、空論だよな! <巷の声> 「愛」は、「欲望」で有り、捨て去るべき物なのか? 親鸞様が、妻帯を 実行されたのはなぜなのか? 「ニーチェ」が「神は死んだ」と言うのと、 全く同じようにも思えますが・・・・・・・・。 「弥陀の目当て=正機 は何か」/「私は正機か?」・・・・・・・・・・・ 「愛」は、どうも「無条件」ではなく、「私に合う相」の様ですね! 「私に合う相手を見つけた」と言う「よろこび=自慢・傲慢・身勝手」 であることを戒めたいものです。 (本来的に、錯覚?なのですから。 但し、この錯覚は、「=人間」という程度の意味です。ご了承を!) 「 |
バランス |
{バランスがくずれたら、必ず想い出すよ} 仏教の基本は、「中庸」。 極端を戒めているわけだ! だけど・・・・・・・・ <何もしないで、何も動かないで、真ん中に>ということはあり得ない。 右に動き、左に動き、前に出て、後ろに引いて、上へ飛び、下へ潜りして はじめて、真ん中辺が、わかってくるわけじゃないか。 頭の中だけじゃこの 距離感はつかめないと思うよ。 また、両極端を口先で批判すれば、中庸なんだ というのも、大きな間違い。 現実は、みんな偏っているのよ。 いろんな正当化の理屈をこねてもね。 例えば、問題の「リストラ」でも、否応なくする側と、される側に分かれちゃう。 「オリンピック」では、記録は、ある種の連続値と見えるけど、現実は、メダル をもらう人と、もらわない人になっているし、家庭では、お洗濯をする人と、 してもらう人、受験では、受かる人と、落ちる人てな具合に。 ( いいとか、悪いとかの判断をしているわけじゃないよ) だから、中庸というのは、現世的な連続値の真ん中にいるということ ではなくて、必ずどちらかに揺れざるを得ないという自分を、揺れの幅 もろともに見るということじゃないかな。 あえていえば、この揺れの幅が 大きいほど、「やさしく」なれるのかもしれないね。 お寺は、このバランスを取り戻す場でありたいと思う。 否応なく揺さぶられ こねくり回されてしまう現世で、一生懸命生きて、自分の位置がわからなく なったら、無理に正当化の理屈をつくったりして、何となく安心(どうせ一時) を得ようとするのではなく、お寺を思い出してよ! お寺は、いつでも、誰でも、「ようこそ」!! みんな元気で、社会の第1線で活躍している間に、この「バランス」感覚を 練習しておいて欲しいね。 いずれ、バランスが崩れるときがあるのだから。 今、この練習をしておかないと、いざというときに大変だよ! かといって、来世・来世ばかりじゃ、これもアンバランス。 決して動かない ご法と、揺れる現世(ここで生きている)のバランスが大事。 <巷の声> 限りない欲望(若干妥協して目標を調整するでしょうが)の実現が、現世で 出来なくなるとき、また作り上げ来たはずのいろんな「構築物」が、砂上の楼閣 であったと気づく時が来るのでしょうね。 今でも、周りにはたくさんの例が見える はずですが、「まだまだ人ごと」で、自分事とは思えないのが現実ですね。 そういえば、綱渡りで使う棒は、すごく長くて、やじろべえ状態ですね。 さーて、余裕のあるうちに、練習・練習! まずは、動いて、幅を広げようかな、(幅なんてあったかしらん? う〜む。) |
スケジュール |
{「スケジュール通りに」/「優先順位をつけて」 −−−−そんなもの、役に立つわけがないよ!} |
立体と平面 |
{自分のことは「立体」を主張、人のことは「平面」に決めつけ!} |
あの世 |
{「この世」のつなぎが「あの世」。 「この世」で精一杯なのに、「あの世」のことをはからえるの??} |
動けば 溶ける |
{「4畳半での悩み??」 動けば溶(解)けるさ!} |
執着 |
{「執着を無くせ」なんてとんでもない。執着こそ信の種} <前段> 本堂を建て替えると決めたとき、実は悩んだ。一つは、前本堂の建設に参加された 方達のお気持ちに対して、ご納得いただけるのかどうか?、もう一つは、建設費用に ついて、前述の問題を含め、ご寄付をお願いする形をどのようにすべきなのか? 結局、いくつかある選択枝から、今回の形を選んだ訳だけど、ベストと信じている。 「本堂は、みんなで作るもの。 みんなが参加してできたものでなければならない」と いう大前提から、「本堂建設へのご寄付」をいただく事にした。 日頃のお参りでの、お布施の集積でやるべきとの考えもあるわけだが、(確かに若干 時期は遅れるけれども、可能な事です。) それでは、自分が参加して建設したという 意識が、必ずしも確かではないように思う。 参加意識を確かにするには、(額の問題 ではなく)「目的のはっきりしているお布施」の形を取る事が大事であると思ったわけ。 「私が参加して出来た本堂」という「執着心」こそが、また「信心」の要素・ご縁になると 考えさせていただきました。 皆様のご協力には、本当に感謝申し上げます。 <後段> 「愛別離苦」: 愛する者と分かれなければならない時の苦痛は、本人でなければ 分からない。 でも、ほとんどの人が経験し、または、経験するものですから、差こそ あれ、極めて一般的な状況といえます。 愛は、「執着」の最も大きなものの一つです。 夫婦愛・子を思う親の愛・親を思う子の愛・肉親への愛・ペットへの愛など、別れ なければならないときに、「愛」=「執着」の大きさに気づき、驚いてしまいます。 この「悲しみ」・「苦しみ」が、自分の限界を気づかせて下さるものであり、しいては 法への帰依の因となるのではないでしょうか? <巷の声> キリスト教では、「神の愛」・「神への愛」と言うようですが、これも「執着」の一つと いえるのでしょうか? 他力の信心は、「執着」を一因として、「限界」に気づき、「お任 せさせていただく」ということになるのですね。 「お任せ」は、「執着」ではないのですね。 |
坊主の方が逃げ回っている |
{大衆が来ないんじゃないよ!坊主の方が逃げ回っているのさ!} 社会人の方達は、いろいろな環境にあり、確かに、法というお育ての場との関係も、 さまざまなわけで、坊主の側から言えば、決して都合が良い訳じゃない。 まあ、実を言えば、坊主も生身なんで、「いやんなっちゃう」場面もあるわけよ。 だけどな、そこで逃げちゃあどないもならんだろが。 いつも、大衆としての自分という 自覚と、その「お取り次ぎ」としての坊主という自覚の間を揺れてないといかんのよ。 この揺れは、一段高いところにいるだけでも駄目だし、葬儀屋だと卑下し、あきら めてしまっても、出てこない。 大変でも、疲れても、いつも坊主として、「お取り次ぎ」 の僧として、但し、目線は一社会人として、社会人の方と話し合える場がないといかん のだと思う。 とは言え、坊主の集まりに安住し、葬儀に集中して、高い位置を保つ のが楽は楽なんだけどね・・・・・・・・俺は、これじゃあ駄目なんだよな! 結局、揺れがみんなから見えるようになってないとだめなわけで、これが結構大変 なんだと思う。 自分をさらけ出さなくちゃならんのだから、繊細な(?)俺だって、 傷つく こともあるのよ! それが怖くてか、あるいは、単に話を合わせていくのが 面倒だからか、忙しさにかまけてか、いずれにしろ、「逃げている」ことをほとんど意識 できないままでいるのかもしれん。 小さく なまんだぶ・・・・なまんだぶ <巷の声> 今、僧侶の方と話し合いたいと思っている方は、結構多いと思います。 理由は様々で、決して、信の話ではなく、ご利益であり、現世的人生相談かも 知れません。 だけども、入り口は、そんなものです。 そこから、どこへ行けるのかが、「お取り次ぎ」のお役割であってほしいものです。 追伸: いつも、正見さんを 「酒の肴」にして申し訳ないことです。 (この肴、実に美味しいので、ウ〜ム・・・ なかなか止まないかしらん!??) |
門徒が主役 |
{「お寺」という場は、文字通りすべてが、門徒・一般大衆のものだよ!} 法座や、イベントのあと、残っているのが僧侶ばかりという場面に結構出くわすけど、 こんなのはおかしいよ! もちろん、僧侶が「反省?・懇親」をすることを否定するわ け じゃあないけど、門徒さんが<法とのご縁を結び・深める「一大事」の場>という 意識が感じられない。何か、一方向的でやってあげてるみたいな心がないだろうか? (かく言う俺もそういう心が湧いてくる。 なんまんだぶ・ごめんさい だけどね。) 僧侶が、<お取り次ぎ>を忘れたんじゃあ、はなしにならんよ。 <巷の声> 門徒・大衆に、参加の場・位置・お役割(世情感覚でわかる)を、 与えてくだされば、皆さん喜んで参加すると思います。 正見さん、あなたは 偉い。 あなたは、いつも一生懸命、みんなに何かしら お役割をしてもらうことを考えていますね。 それが、阿弥陀の呼び声・光という ことではないでしょうか? 「宗教的な実感・体感」が積み重なるのかも!? |
だまれ! うるさい! |
{「黙れ!」とでも言わないとおまえらの話は終わらない。} 通常、上位者または強権者が、下位者又は弱者に対して、発言を封じる合図(手っ取り早い)ですが、最近では、セクハラの一種として相当に気をつけて使う必要があります。 われわれが、自分のことを話しはじめると、最初は恐る恐る小出しにしていても徐々に乗ってきて、「娑婆の尺度」そのままの善悪感覚で、話が進んでしまいます。更には、「自分の告白」だったはずが、他人事、ひいては「人の批判」になっていることが多いものです。 ★ 「黙れ」は、アミダの「わかりやすい呼び声」かもしれませんね。 <巷の声> 乱用は、いけません。 本当にセクハラになります。 (闊達な発言の場が、萎縮してはつまりません。 慣れない人には注意して。) でも・・・、「黙れ!」を聞くと、ちょっとほっとするのは、私だけでしょうか? きっと、どんどん言っていいのかもね! 言わなくなったら、年老いたことかも! |
捨てる |
{俺に偉いところがあるとすれば、『捨てる』という事かな!} 俺には、立派なところ、得意なことなど一つもないけど、いつもみなさんのおかげさまでやらしてもらっている。 そんな俺をなぜか助けてくださるのは、「全部捨てる」ということじゃないかな。 自慢話になりそうで、はなしずらいけど、『お寺は、一時的な預かりもの』、俺が養子だからじゃなく、(でもそれは強い契機かも知れないが)この考えは、すべての基本になっている。 法人財産的な面/肩書き・名誉の面/世襲的な面、その他あらゆる公的・共同的な事柄は、たとえ今俺の管理下にあるとしても『俺のもの』じゃない。 『俺は、お取り次ぎの一職員』(かっこよすぎるかな?!) でも、お預かりしている以上は、やるべき事はたくさんあるし、現世の経済ルールには、きっちり従わなくちゃならないわけで、実際には、あれやこれや得意じゃないことも、自分で判断・決定しなくちゃならない。 『執着心』は、無いと言えば嘘。毎日が『執着心』のお育ての場だよ! いらいらして、みなさんに迷惑を掛けているのに自分ではどうしようもないこともある。 完全に、自己嫌悪に陥ってしまう。 そこで、また、あなた達とこうやって『ぐだぐだと?』話ができるのが救い、俺の原点を思い出させられるというわけ。 <巷の声> 住職得意の逆説論法でいけば、住職にとっては、「捨てる」=「執着」であり、住職が現世に生きるとは、この両方を行ったり来たりする事以外には無いということなのでしょうね?! われわれは、「俺のもの」=「執着」で、どんなものでも手放すのは大変です。 だからこそ、具体的な「捨てる」姿に感動し、往生というミラクルを期待する気持ちがわくのでしょうか? |
一本釣り (1988年) |
{法の仲間を増やすのは、「一本釣り」しかないよ!} 網を使ってごっそり「サンマ」を取るのとは違う。 ほんとにわずかなきっかけ(葬儀・法事関係がほとんど)から、話し込み・飲み込み(得意でもそろそろからだに注意) 相手の常識が逆転してびっくりするくらいまで、つきあわないと釣ったことにはならないよ! だから、一対多の法座でなんか「法は伝わらない」。 一対一の「相伝」しかないよ。 それを、法座で、というのは怠慢だ! みんな違うんだよ。 お育てが違うんだよ。 気づき方が違うんだよ。 プライドも自力作善の傲慢さも、一度や二度の法座で、どないもならん。 これをぶっこわさないと、「一心一向に帰依」など夢のまた夢だろう! <巷の声> とはいえ、住職一人ではできる数が知れています。 法座も、法事も、子供会も、そのほか お寺に人が集まるすべての場が、きっかけであり、その場を増やし、集まる人数を数えるのも、活動の目標にはなっていいのではないですか? 、 一方、それだけでは「法は伝わらない」のなら、住職が相伝した相手はどうなっていますか? 別の相手に相伝していますか? 「相伝」は連続・継続が命?! → 住職がよく言う、『まずは家族にも伝えてくれ』ということですね! |
阿弥陀くじ |
{救いは阿弥陀くじの様に、一対一で、必ず各人とつながっている} 阿弥陀仏の後背が放射状にであり、「くじ」の線の引き方ににているところから「アミダくじ」と言われる。 さらに、阿弥陀の後背は「なぜ、線なのか?」−−「一対一でつながっている」というのが味噌。 どこがどうなっても(あみだくじでは、横線を追加するが)必ず つながっているということで、「アミダくじ」とは名付けたり。 ぺぺんぺんぺん! <巷の声> 凡夫では、直接弥陀光を見る・感じるのはほとんど不可能?? それを、保証し、実践するのが、一本釣り=相伝ですね。 あみだくじの「横線」になるのかな?? |
一本釣り PART2 (2002年) |
{法話での話は、1対多じゃなくて、結局は1対1になってるんだよ} 定例法話会の講師や、お朝事での法話をやるようになってきて、いつも1対1、誰かに対して話しかけるという自分を感じている。若い頃は、「説得しなきゃ」みたいな気負いが強かったけど、(傲慢さかな)この頃は、「参加下さってるみなさんの方が、間違いなく1対1で聞いて下さるんだ」と、なにか<お任せしていいんだ>という安心感みたいなものに気がつかされるときがある <人>と<法>の「お取り次ぎ」が仕事だとしても、一方的に「俺が」引っ張っていく様なものとは、はっきり言って違ってきてるな。 とはいえ、まだまだ「俺がやらなきゃ」は、なくなりそうもないけどね。 <巷の声> 「1対1」の関係は、「恋愛/嫉妬/憎悪」と同じ心的構造を持っている様におもえます。 『お取り次ぎ まずは住職を 好きになり』 社会性を持って生きている人間が、法に心的に参加(信)するプロセスの一つのスタートが、ここに見えるような気がします。 きっと、次が『家族』・『家族的グループ』感であり、これと『法の世界』がどこかで同致されて『信』に至るという心的なプロセスが考えられます。 もちろん、別のプロセス、例えば、『個から直接、法へ』もあるでしょう。 |
| ◆ 壮年会 に関するお問い合わせは、下記へ |
|
浄土真宗本願寺派 上正寺 (東京教区 鎌倉組) 〒253 神奈川県茅ヶ崎市 小和田2丁目 12-73 TEL: 0467−51−2138 FAX: 0467−51−2139 mail: 0514009301@jcom.home.ne.jp ☆ E−MAILの方は→ |
|